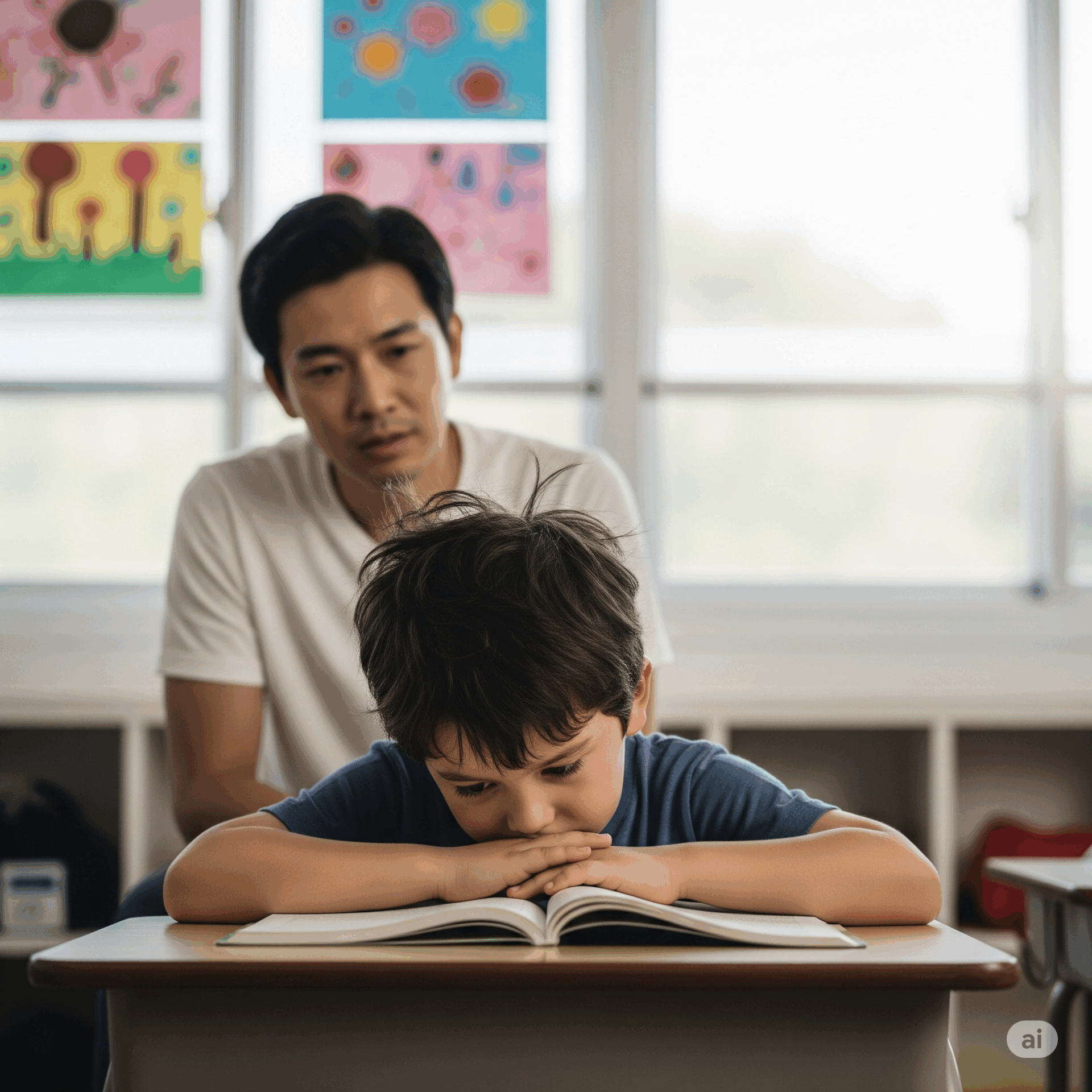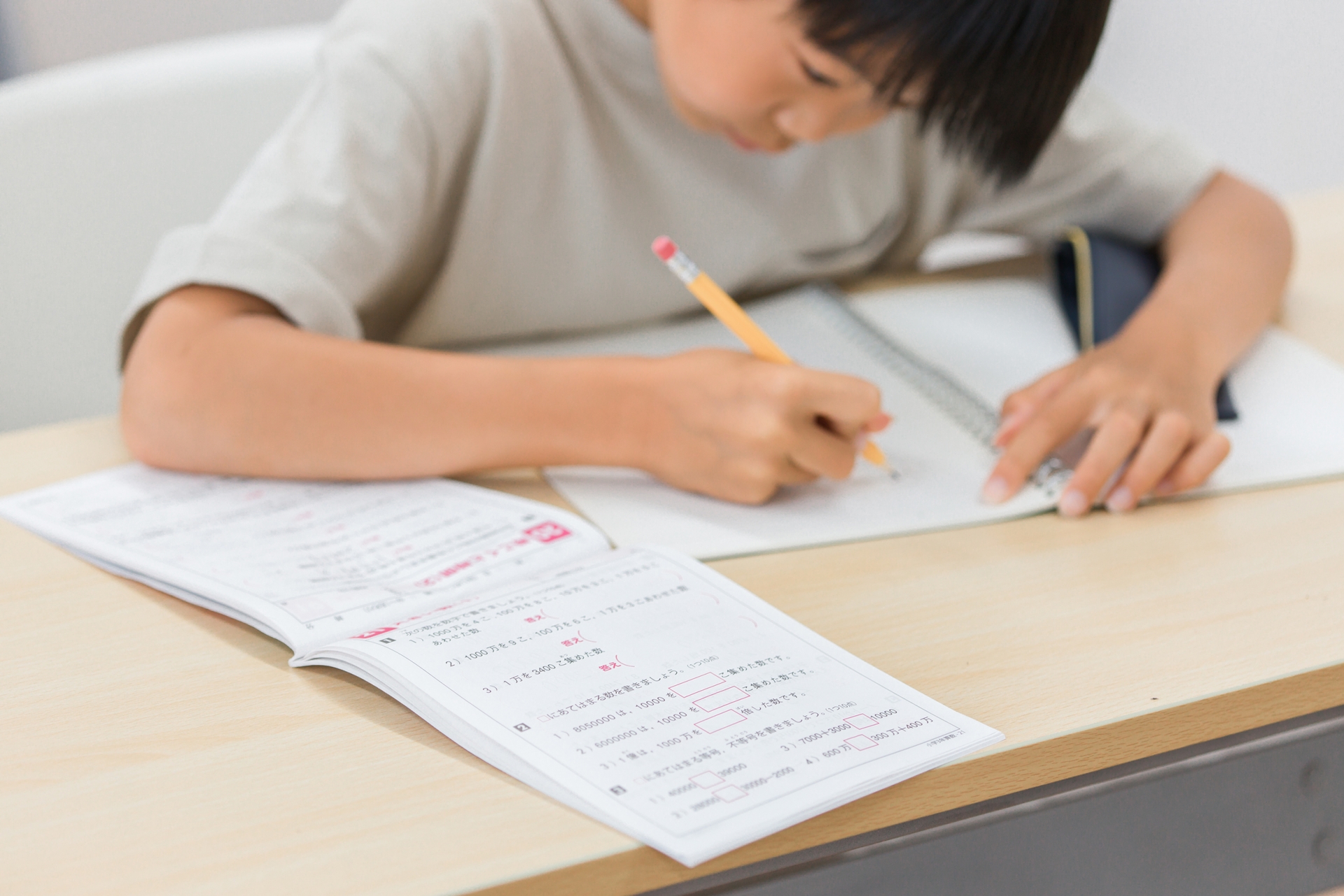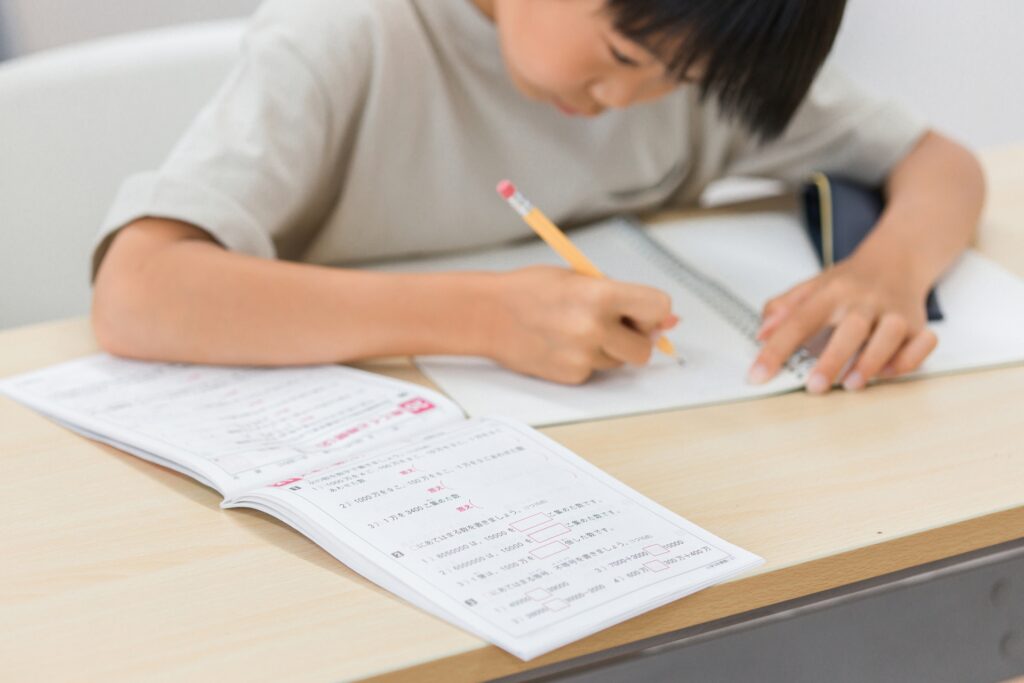新学年がスタートして、あっという間に2ヶ月が経ちましたね。
お子さんも新しい環境に少しずつ慣れてきて、落ち着いた日々を過ごされていることと思います。
でも、この時期、なんだかお子さんの様子がいつもと違うな、と感じることはありませんか?
小学校の子育てで、特に6月は「魔の時期」と呼ばれることがあるんです。
6月、なぜ子どもの様子が変わるの?「魔の時期」の理由
この時期、保護者の方からよく聞かれるお悩みがあります。
- 些細なことでイライラしている
- 学校の話をあまりしなくなった、聞いても教えてくれない
- 朝、なかなか起きられなくなった、体が重そう
- 「学校に行きたくない」と登校を渋り始めた
- 家で癇癪を起こしたり、荒れたりすることが増えた
もし、こんなふうに感じているなら、
それはお子さんが「素」を出しているサインかもしれません。
なぜ6月にこのような変化が起こりやすいのでしょうか。
- 梅雨によるストレス
6月は梅雨の季節。雨の日が続くと、外で元気に遊べない日が多くなりますよね。室内で過ごす時間が長くなると、子どもたちは有り余るエネルギーを発散できず、校内や教室を走り回って思わぬ怪我やトラブルに発展することもあります。 - 新生活の疲れ
4月、5月と新しい環境で頑張ってきた子どもたちは、この時期に心身の疲れが出てくる子も少なくありません。天気が悪いと気分も落ち込みやすく、登校を渋り始める子も出てきます。 - 慣れとクラスの状況
新しいクラスや先生にも慣れてきて、「もう頑張らなくていいや」と、これまで抑えていた感情が表に出てくる時期でもあります。この時期はクラスが少し荒れ始めることもあり、学校で我慢している子も少なくありません。 学校で頑張って抑えていた気持ちやエネルギーが、ご家庭で爆発してしまう。つまり、家で荒れたり、癇窶を起こしたりするお子さんが増える時期でもあるんです。
お子さんがこれまでと様子が違うな、と感じる保護者の方はきっと多いのではないでしょうか。
子どもの「魔の時期」を乗り越えるために保護者ができること
もし、お子さんに何か気になる変化が見られたら、
まずは「今はそういう時期なのかもしれないな」と思い出してみてください。
そして、保護者の皆さんがお子さんに寄り添うために、できることがあります。
- 普段以上に「よく観察すること」
学校での出来事や、お友だちとの関係、先生とのやり取りなど、お子さんの小さな変化を見逃さないように、そっと見守ってあげてください。いつもよりほんの少し、お子さんの表情や行動に意識を向けてみましょう。 - 「話にじっくり耳を傾けること」
お子さんが一番安心して過ごせる場所は、やっぱり家庭です。
お子さんが「学校でこんなことがあったよ」「今日ね、こんなことが嫌だったんだ」と話してくれたら、どんなに些細なことでも、ぜひじっくりと耳を傾けてみてみませんか?話を遮らず、「うんうん」「そうだったんだ」と相槌をうつだけでも大丈夫です。 - 安心できる居場所であること
「疲れたな」「もう頑張れないな」と感じたときに、安心して話せる場所があること、そして、その話を受け止めてくれる人がいること。それが、子どもたちの心を支える大きな力になります。
ご家庭を、お子さんにとっての「心の避難場所」にしていけるといいですね。
子育ての悩みを一人で抱え込まないで
この「魔の時期」を乗り越えるために、ご家庭でできることはたくさんあります。
焦らず、お子さんのペースに合わせて、寄り添っていきたいものです。
もし、お子さんの様子が心配なことや、ご家庭での対応に悩むことがあれば、一人で抱え込まずに相談してください。
岡崎ほっこり学舎は、元小学校教員であり現役スクールカウンセラーが、教育と心理の専門家として、お子さんの健やかな成長をサポートしています。
お子さんの登校しぶりや、家庭でのイライラ、学習面での不安など、どんな小さなことでも構いません。
どうぞお気軽にご相談ください。