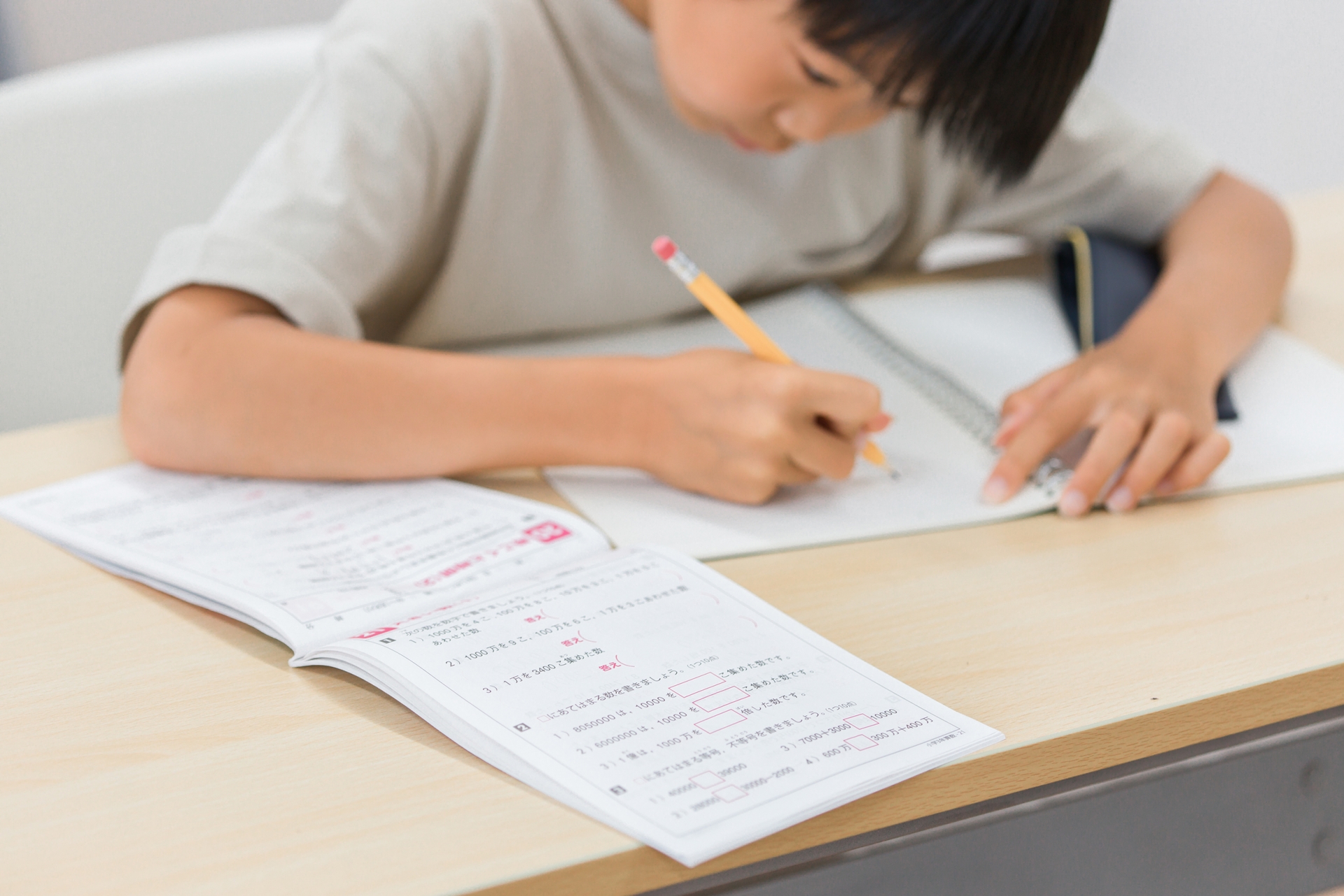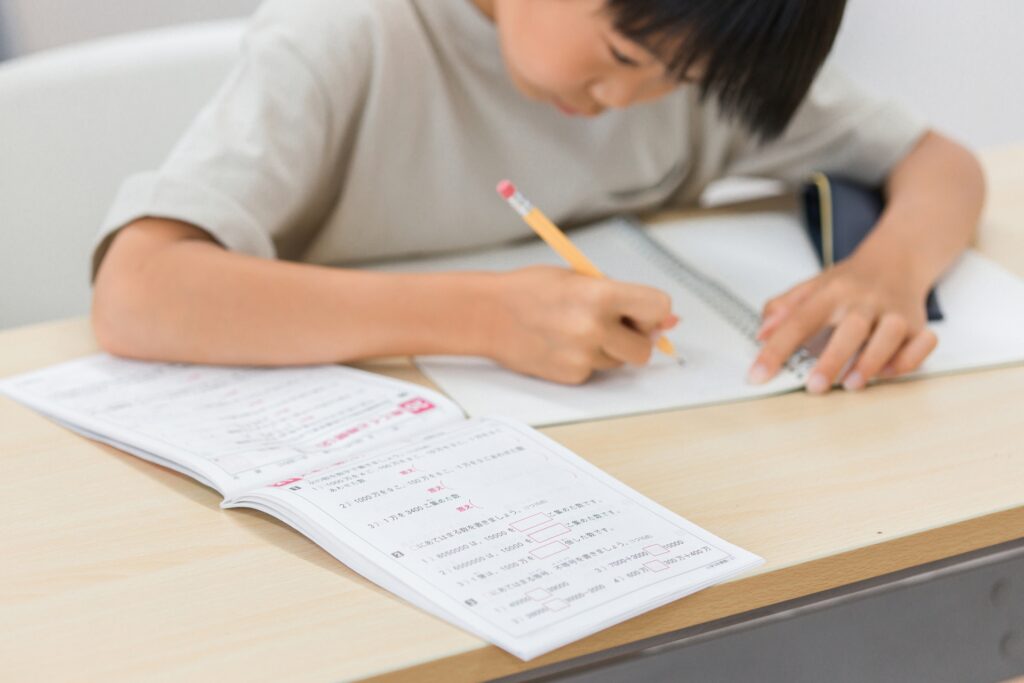「あぁ、また夏休みが来る…自由研究、どうしよう!?」
毎年、夏休みが近づくと、多くの保護者の方からこんなため息が聞こえてくる気がします。
テーマ探しに始まり、途中で子どもがやる気をなくしたり、結局親がほとんど手伝う羽目になったり…。
「子どものため」とわかっていても、正直なところ、ちょっと億劫に感じる方もいるかもしれませんね。
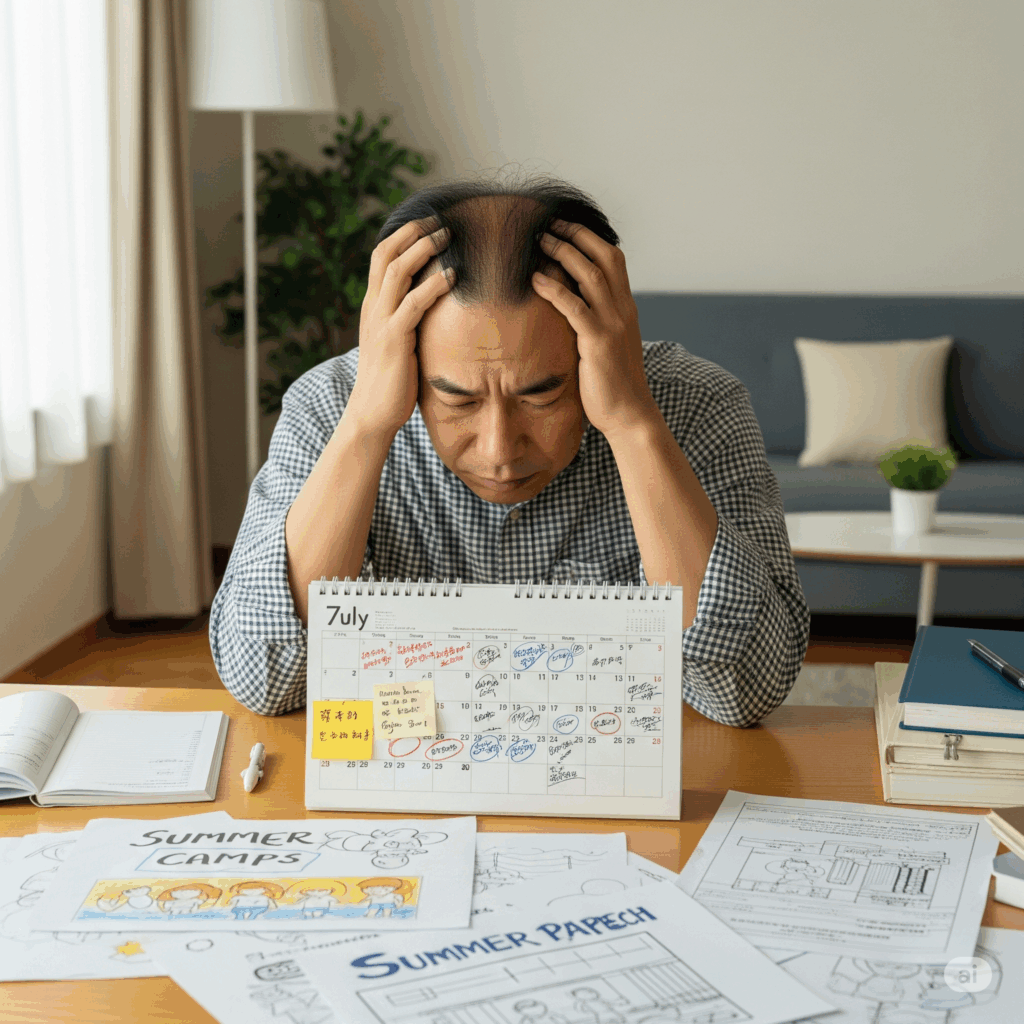
今回は、元小学校教員であり、現役スクールカウンセラーとして多くの親子と関わってきた私が、「夏休みの自由研究」を親子にとって最高の学びと成長の時間に変えるヒントをお伝えします。
キーワードは「問いかけ」。
これを知れば、もうテーマ探しに悩むことはありません!
自由研究は「問い」から始まる!~わが子の「なぜ?」をキャッチしよう~
自由研究の本当の面白さは、子ども自身が「なんでだろう?」「どうしてこうなっているんだろう?」という疑問(問い)を見つけ、それを自分の力で解き明かしていくプロセスにあります。
知識を詰め込むことだけが学びではありません。
自ら問いを立て、探求する力こそ、これからの時代に必要な能力なんです。
では、どうすれば子どもの「問い」を引き出せるのでしょうか?
ステップ1 身の回りの「興味があるもの」を観察する
まずは、お子さんが普段何に興味を持っているか、何を「不思議」だと感じているかにアンテナを張ってみましょう。
特別なものでなくて大丈夫。日常の中に、自由研究のヒントは溢れています。
- 食卓のバナナ いつも食べているけれど、よく見てみると…?
- 公園の石ころ ゴロゴロ転がっているけれど、一つ一つ違う形や色をしているね。
- 自分が使っている鉛筆 毎日使っているけれど、どうやってできているんだろう?
お子さんが何かにじっと見入っていたり、「これ、なあに?」と聞いてきたりしたら、
それは最高のチャンス!
「〇〇について、どう思う?」「これ、不思議だね」と、ぜひ声をかけてみてください。
ステップ2 その「もの」に「問い」を投げかける
お子さんが興味を持った「もの」が見つかったら、
次にすることは、その「もの」に対して一緒に「問い」を投げかけることです。

例えば、
「バナナ」なら…
- どうして黄色いの?(なんで?)
- どうして長細いの?(どうして?)
- どうして黒い点々ができるの?(どうして?)
- どうして最初は緑なのに、黄色に変わるの?(どうして?)
「鉛筆」なら…
- どうして木でできているの?(なんで?)
- どうして丸や三角や、六角形とか、いろんな形があるの?どうやってあの形になるの?(なんで?どうやって?)
- どうしてあの長さなの?(どうして?)
- 芯は何でできているの?(なんで?)
このように、「どうして?」「なぜ?」「どうやって?」といった言葉を使って、たくさんの疑問を書き出してみましょう。
親子で一緒に「変なこと聞いちゃったかな?」なんて笑いながら、自由に問いを広げていくのがコツです。
大人が「まさかそんなこと?」と思うような子どものユニークな問いこそ、新しい発見の宝庫になることもありますよ!
問いが見つかったら、いよいよ研究スタート!~親の「絶妙な」サポート術~
問いが見つかれば、もう自由研究は始まったも同然!
あとは、その問いをどうやって解き明かすかを考え、実行に移すだけです。
ここからは、保護者の皆さんの「絶妙な」サポートが子どものやる気をぐんぐん引き出します。
ステップ3 「どうすればわかるか」を考える
問いが出せたら、次は「どうすればその答えがわかるだろう?」と一緒に考えてみましょう。
- 調べてみよう!
図鑑や本を読んだり、インターネットで検索したり。図書館の司書さんに相談してみるのも素晴らしい方法です。 - 実験してみよう!
実際に手を動かして、仮説を検証してみる。 - 観察してみよう!
じっくりと時間をかけて、変化や特徴を記録する。(問いによっては、かなり時間がかかるものもあるので、できるだけ早めに取り組むのがいいと思います。) - 作ってみよう!
何かを自分で作り出すことで、仕組みを理解する。 - 聞いてみよう!
そのことに詳しい人(専門家、お店の人、工場の人など)に直接話を聞いてみる。
「え、作っている人に聞いてみようか?」「〇〇科学館に行ってみる?」といった、具体的なヒントをさりげなく与えてあげてください。
子どもが「わからない!」と立ち止まったら…
子どもは、調べても答えが見つからなかったり、実験がうまくいかなかったりすると、
一気にやる気を失ってしまうことがあります。そんなときこそ、親の出番です。
「あれ?難しいね。じゃあ、これはどうやったら解明できるかな?」
「よし、大人も一緒に考えてみよう!」
と、一緒に悩む姿勢を見せてあげましょう。
決して答えを教えるのではなく、ヒントを出したり、「じゃあ、こんな方法もあるんじゃない?」と別の視点を提供したりするんです。「え、私も初めて知った!」といった驚きを共有することも、子どもの探求心を刺激します。
この「効率が悪い」と感じる時間こそが、子どもが自分で考え、壁を乗り越える力を育む貴重な時間なんです。
そして、親が真剣に寄り添うことで、子どもの心に再び意欲の火がつき、自ら動き出すはずです。
親の「絶妙な」サポート術の具体例
- 資料集めの手伝い
必要な本を一緒に探したり、インターネット検索で適切なサイトを見つけるのをサポートしたり。 - 安全確保
実験など、危険が伴う作業は必ず大人が付き添う。 - 記録の促し
毎日少しずつでも、観察日記をつけたり、写真を撮ったりするように声かけをする。 - スケジュール管理
夏休みの終わりになって慌てないよう、「今日はここまでやってみようか」と声かけをする。 - 完璧を目指さない
「もっとこうしたら?」と口を出しすぎず、子どもの発想やプロセスを尊重する。
大切なのは、「親が代わりにやってあげる」ことではなく、
「子どもが自分でできることを見つけて、サポートする」ことです。
最終的な成果物の出来栄えよりも、子どもがどれだけ「面白い!」と感じ、
夢中になって取り組めたか、そして、どれだけ「自分でできた!」という自信を得られたかが重要です。
この体験がのちに大きな成長に繋がります。

自由研究をさらに「面白い」にするヒント
せっかくの自由研究、子どもがさらに「面白い!」と感じられるような工夫をしてみませんか?
発表方法を工夫しよう
研究が終わったら、いよいよ発表です。模造紙にまとめるのも良いですが、他にも様々な方法があります。
- 写真や動画で記録
研究のプロセスを写真や動画で残しておくと、後で見返したときに楽しい思い出になります。簡単な動画にまとめて、家族で鑑賞会をするのも良いですね。 - プレゼンテーション
家族の前で、発表会を開いてみましょう。身振り手振りを交えながら、自分の言葉で説明することで、発表する力が育ちます。 - ポスターやミニ冊子
絵やイラストをたくさん使って、自分だけのオリジナル作品を作るのも楽しいですよ。
「失敗」も立派な研究の一部!
実験がうまくいかなかったり、思った通りの結果が出なかったりすることもあります。そんな時こそチャンスです。
「なんでうまくいかなかったんだろう?」「次はどうすれば成功するかな?」
と、失敗の原因を一緒に考えてみましょう。失敗から学ぶことこそ、最高の学びです。
まとめはお子さんが苦手な段階でもあります。ここもおうちの方のサポートが必要場面でもあります。
夏休み自由研究は「親子の成長の記録」
夏休みの自由研究は、子どもが「なぜ?」を追究し、自分で答えを見つける力を育む絶好の機会です。
そして、親にとっては、子どもの「探究心」や「創造性」、そして「自信」が育っていく過程を間近で見守り、
一緒に喜び合えるかけがえのない時間でもあります。
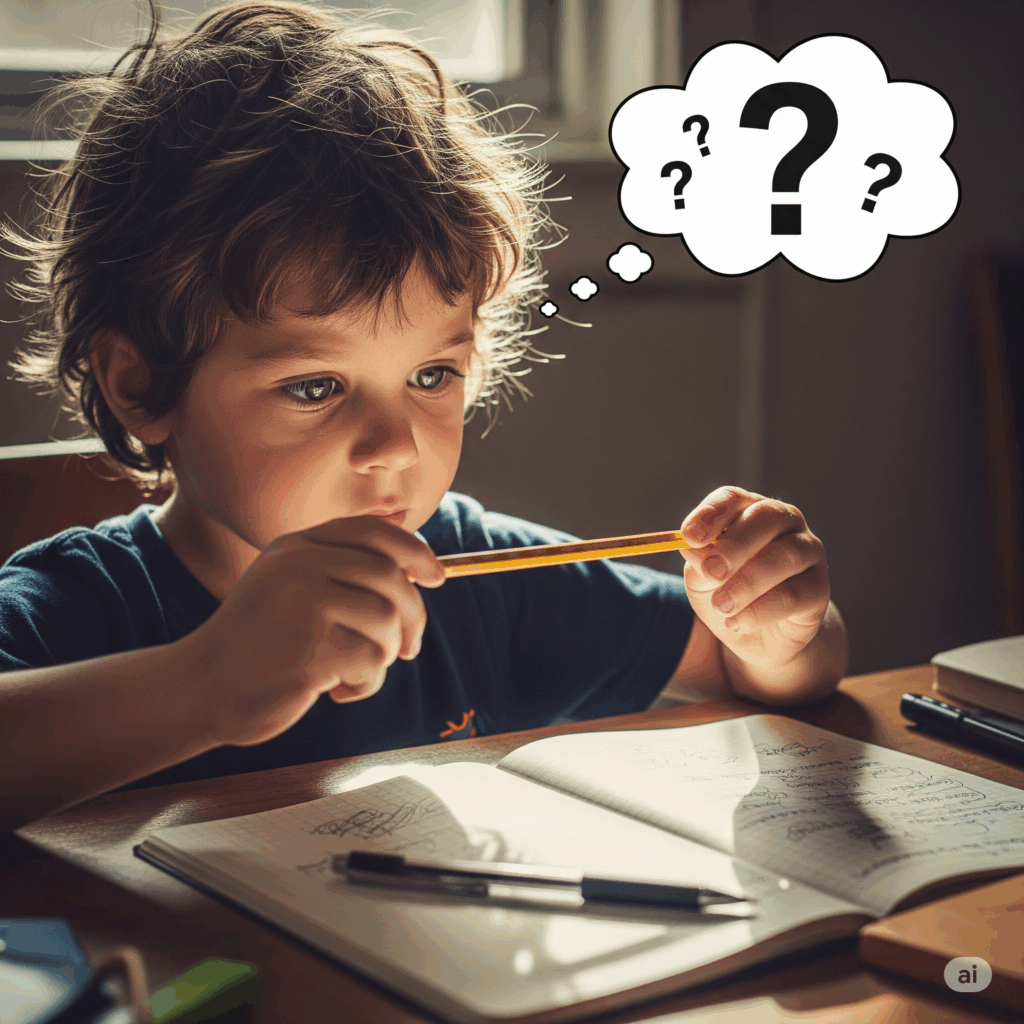
「効率の悪い時間」と思うかもしれませんが、親子で共に悩み、共に発見し、共に成長するこの時間こそ、
最高の親子の思い出となり、子どもの心に深く刻まれることでしょう。
完璧な自由研究を目指す必要はありません。
一番大切なのは、お子さん自身が興味をもって取り組み、「できた!」という達成感を味わうことです。
そのためには、人から与えられた問いを追究していくのではなく、自ら生み出した問いを追究していくことです。
さあ、この夏はぜひ、お子さんの「なんで?」の声に耳を傾け、親子で一緒に「面白い!」を探す旅に出てみませんか?


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/151c2a63.1680c089.151c2a64.6973ca4e/?me_id=1213310&item_id=14192350&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1859%2F9784092131859_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/151c2a63.1680c089.151c2a64.6973ca4e/?me_id=1213310&item_id=20339928&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3009%2F9784052053009.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/26870a9b.c9684682.26870a9c.e6b78ac3/?me_id=1210719&item_id=10001308&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmarutomi-kyouzai%2Fcabinet%2Fkenis001%2Fkk577.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/151c2a63.1680c089.151c2a64.6973ca4e/?me_id=1213310&item_id=19517134&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9713%2F9784065149713_1_40.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)