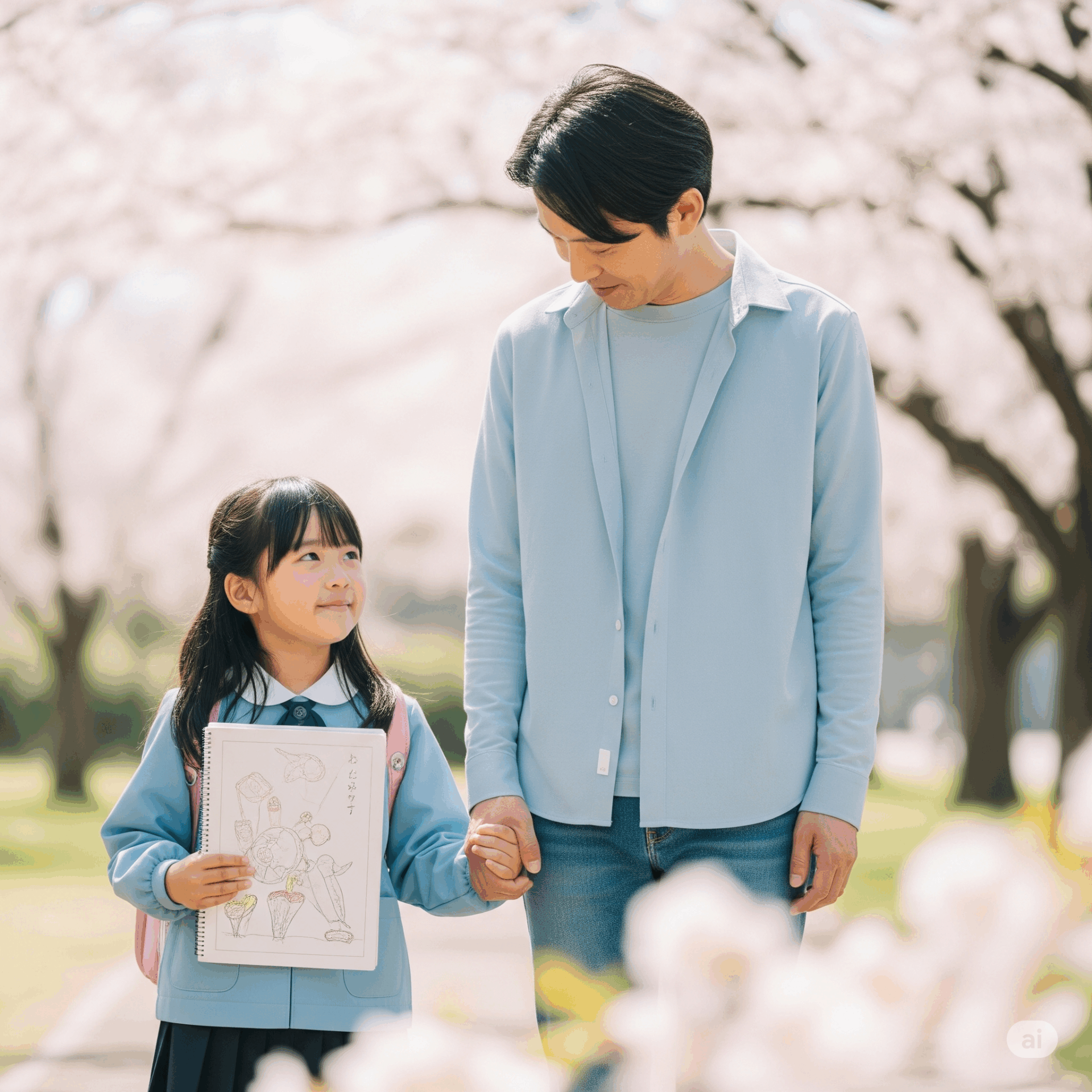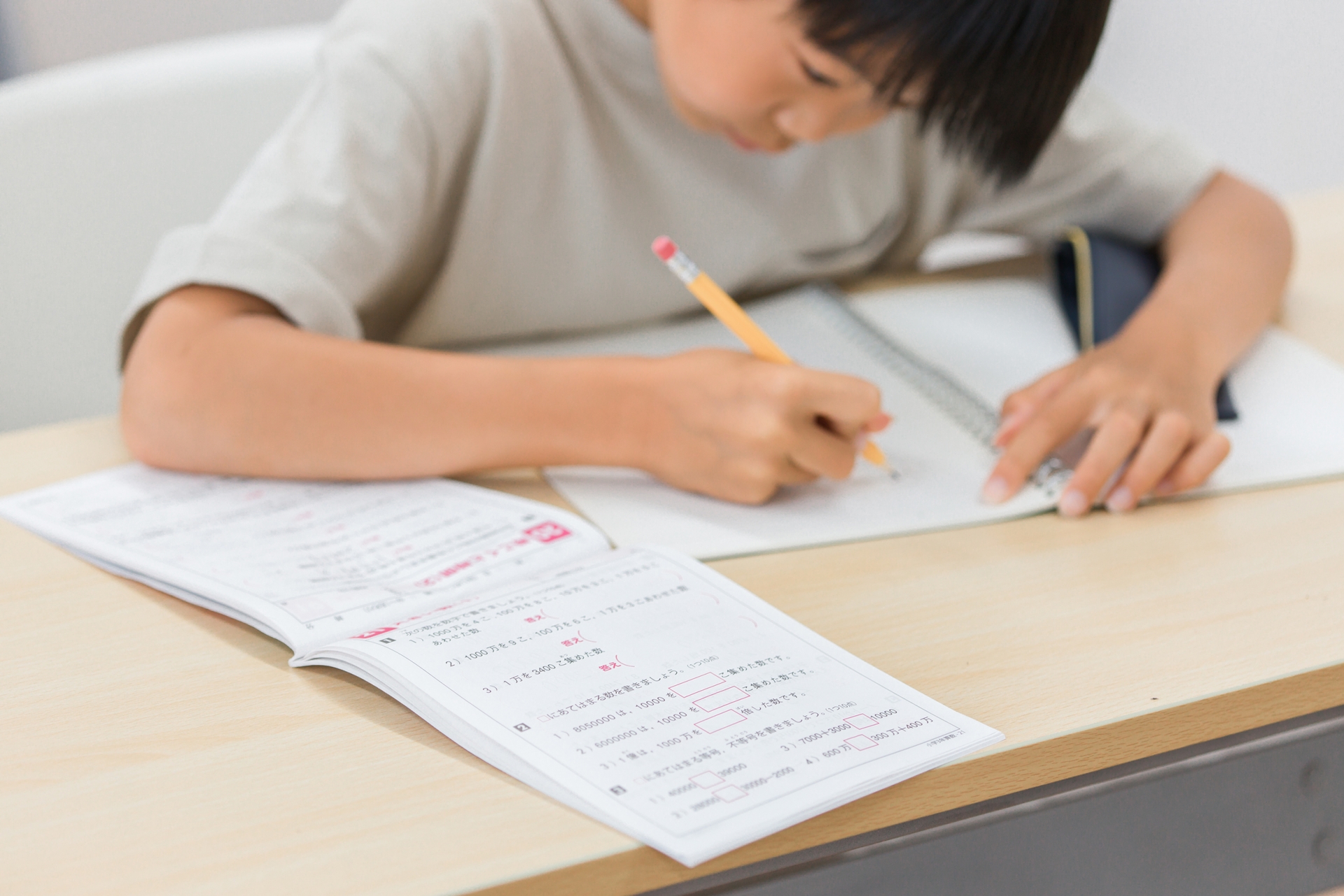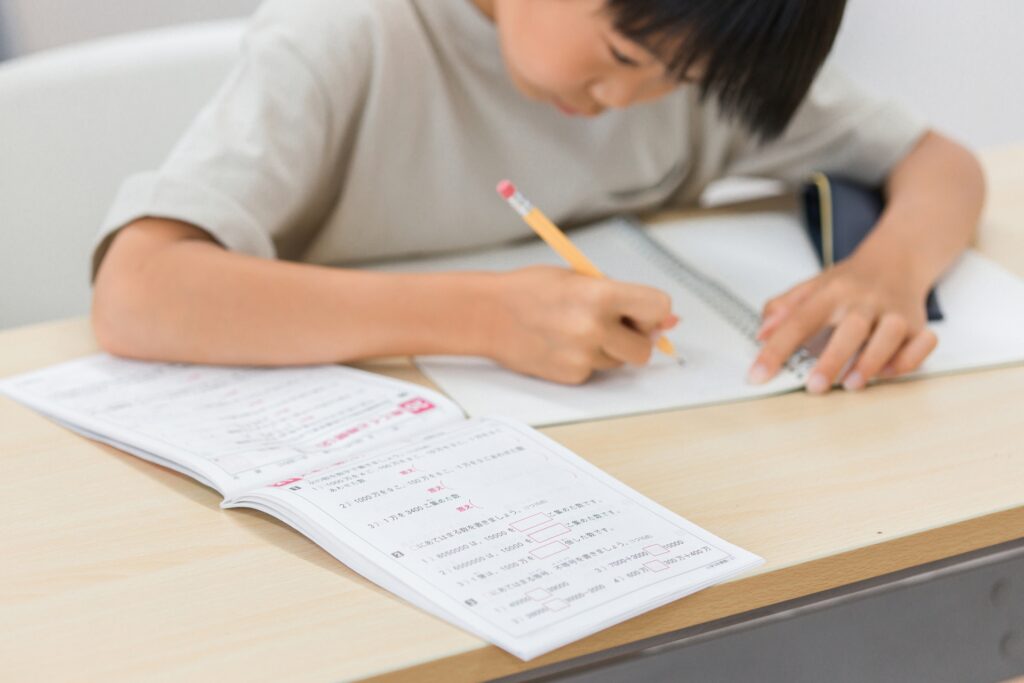「うちの子、学校で何してるんだろう?」
「友達とうまくいってるかな?」
「スマホ、何見てるのか正直、気になる…」
お子さんのこと、心配になる気持ち、私も親として本当によくわかります。
でも、その「全部知りたい」という優しい気持ちが、
もしかしたらお子さんの成長にとって、少しだけ足かせになっていることもあるんです。
岡崎市で「岡崎ほっこり学舎」という小学生向けの学習塾を始めてから、多くの子どもたちや親御さんと出会ってきました。私自身、元小学校教員として20年、今は現役のスクールカウンセラーとしても活動しています。
そんな私の経験と、ちょっとした心理学・脳科学の視点から、
今回は「親子のちょうどいい距離感」について、お話しさせてください。
この記事を読み終える頃には、
お子さんとの毎日が、もっと穏やかで、楽しいものになるヒントが見つかれば嬉しいです。
「知りすぎ」が心を閉ざす?子どもにもある「心のプライバシー」
「子どものことは何でも把握しておきたい」
そう思うのは、親なら当たり前のことですよね。
でも、私たち大人と同じように、
子どもにも「心のプライバシー」があることを、ぜひ知っておいてほしいんです。
アメリカの心理学者の研究でも言われていることなのですが、
親が子どものことに深く踏み込みすぎると、子どもはストレスを感じやすくなったり、
親に対して「なんだか信用されてないな」と感じてしまうことがあるんです。
特に小学校の中学年くらいから、
子どもたちは自分だけの秘密や、
友達との間でだけ盛り上がる話題を持つようになります。
これは、成長の証。
そんな時に親からあれこれ詮索されると、
「全部知られちゃうのは嫌だな」
「信用されてないんだな」と感じて、
心を閉ざしてしまう原因になりかねません。
もちろん、「じゃあ放っておけばいいの?」という話ではありません。
大切なのは、「気にかける気持ち」と「見守る姿勢」の、絶妙なバランスなんです。
【今日からできる!】子どもの自立を応援する親子の距離感3つの秘訣
では、具体的にどうすれば「ちょうどいい距離感」を保てるのでしょうか?
私がこれまで現場で見てきたこと・考えてきたこと・うまくいった事例、そして心理学の視点も交えながら、
すぐに実践できる3つのポイントをお伝えしますね。
1. 「聞く」より「待つ」。話したくなる「空気」を作る
「今日、学校どうだった?」お子さんに毎日こう聞いていませんか?
悪気はないのに、お子さんにとっては「また聞かれるのかな」と、
ちょっとしたプレッシャーになっているかもしれません。
子どもが「話したいな」と思うタイミングって、
親のタイミングとは全然違うことが多いんです。
だから、大切なのは、
子どもが「話してもいいな」と自然と思えるような「空気」を作ってあげることです。
- オープンな質問で、ゆるく誘う
- 「なんか面白いことあった?」
- 「昨日言ってたアレ、どうなった?」
- 「最近、何かハマってることある?」 こんな風に、答えが一つに限定されない、軽い質問を投げかけてみてください。子どもは「答えなきゃ」という重圧を感じず、話しやすくなりますよ。
- 「ながら聞き」も意外と効果的
- 一緒にテレビを見ながらぼそっと
- 夕食の準備をしながら
- 車での移動中 など、子どもがリラックスして他のことをしている時に、さりげなく話しかけてみましょう。ふとした瞬間に、ポロッと本音を話してくれることがよくあります。
2. 「助け舟」はここぞという時に:自分で考える力を信じる
子どもが困っていたり、ちょっとつまずいている姿を見ると、
「なんとかしてあげたい!」って、すぐに手を出したくなりますよね。
でも、そこをぐっとこらえて、少しだけ見守ってみてください。
例えば、友達とケンカした話をしてきた時。
「それは○○ちゃんが悪いよ!」
「こう言えばよかったのに」と、すぐに正解を教えるのではなく、
まずはお子さんの気持ちに寄り添い、自分で考える促しをしてみてはいかがでしょうか。
- 「それで、あなたはどうしたの?」
- 「自分ではどう思ったの?」
- 「どうなったら、一番いいと思う?」
子どもが自分で考え、どうすればいいかを見つけるプロセスを応援することで、
自分で問題を解決する力と、「自分にもできた!」という自信が育まれます。
これは、将来必ず役立つ力になると思います。
3. 「親の感情」は「背中」で語る。生きる姿を見せる
私たち親も、人間です。
疲れてイライラしたり、落ち込んだりすることだって、もちろんありますよね。
そんな時こそ、実は、お子さんにとっての一番身近な「学びの場」になります。
自分がどんな気持ちになって、
どうやってその気持ちと向き合い、乗り越えているか。
それを言葉にして、お子さんに見せてあげてほしいんです。
- 「今日はちょっと疲れたけど、温かいお風呂に入ったらスッキリしたよ」
- 「あの時はちょっとイライラしちゃったけど、深呼吸したら落ち着いたんだ」
親が自分の感情ときちんと向き合う姿を見せることで、
子どもは感情のコントロールの仕方やストレスとの付き合い方を自然と学びます。
これは、お子さんがこれから様々な人間関係を築いていく上で、きっと大きな力になるはずです。
<まとめ>
「信じてるよ」の言葉が、何よりの支えに
今回の話をまとめると、親子の「ちょうどいい距離感」のポイントは、次の3つです。
- 子どもにも「心のプライバシー」があることを理解する。
- 「聞く」よりも「待つ」姿勢で、話したくなる雰囲気を作る。
- 「助け舟」は必要最小限に、自分で考える機会を大切にする。
- 親の感情表現を「背中」で見せて、生きる姿を伝える。
岡崎ほっこり学舎では、子どもたちが「自分はできる!」という自信を取り戻し、学びを楽しいと感じられるよう、一人ひとりに寄り添った指導をしています。私自身、子どもたちの「わかった!」という顔を見るのが何よりの喜びです。
「信じてるよ」
この、たった一言が、お子さんにとってどれだけ大きな心の支えになるか。
ぜひ、今日からほんの少しだけ、お子さんとの「距離感」を意識してみてください。
子育ては、近づきすぎても、遠ざかりすぎても難しいもの。
でも、今回のヒントを参考に、お子さんにとっての“ちょうどいい距離感”を、一緒に見つけていきましょう。
岡崎ほっこり学舎では、お子さん一人ひとりの「わかる!」を引き出し、自信を取り戻すための丁寧な指導をしています。
学習についてのお悩みはもちろん、子育てや教育、お子さんの心のことで気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。元小学校教員・現役スクールカウンセラーとして、私も一緒に考えさせていただきます。
岡崎ほっこり学舎のへお問い合わせはこちらから